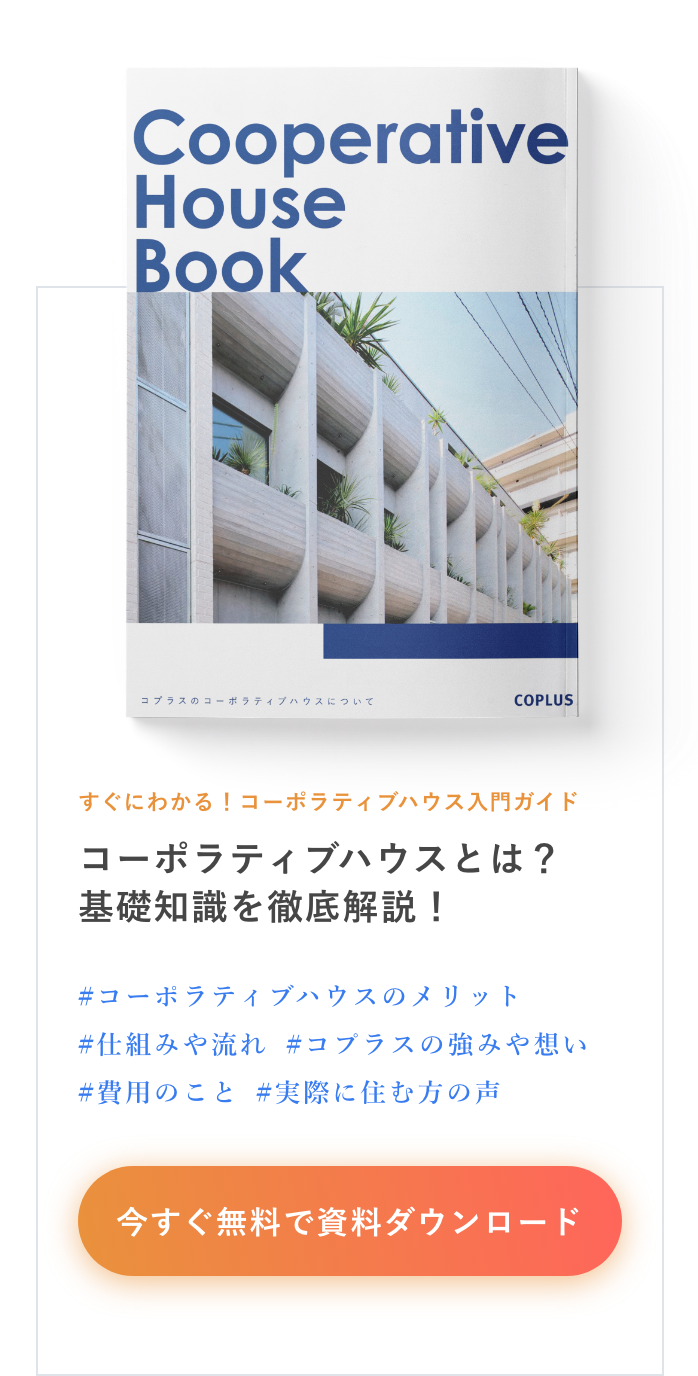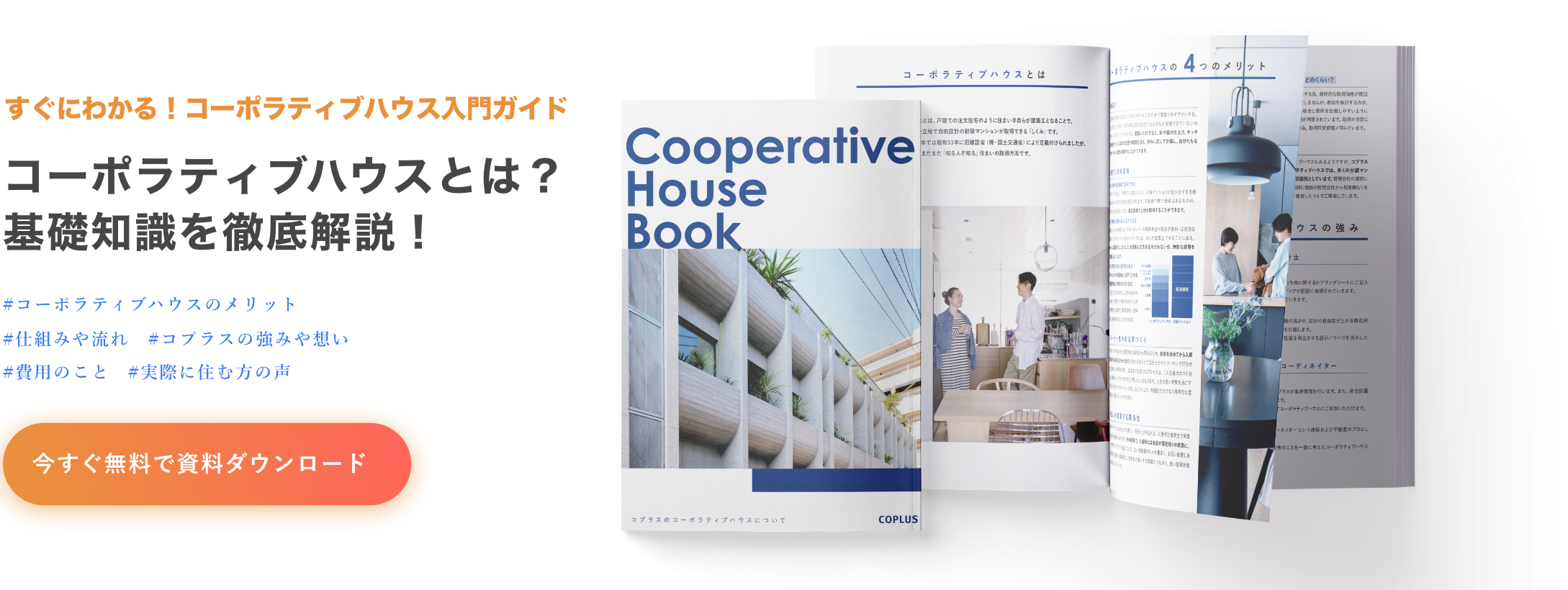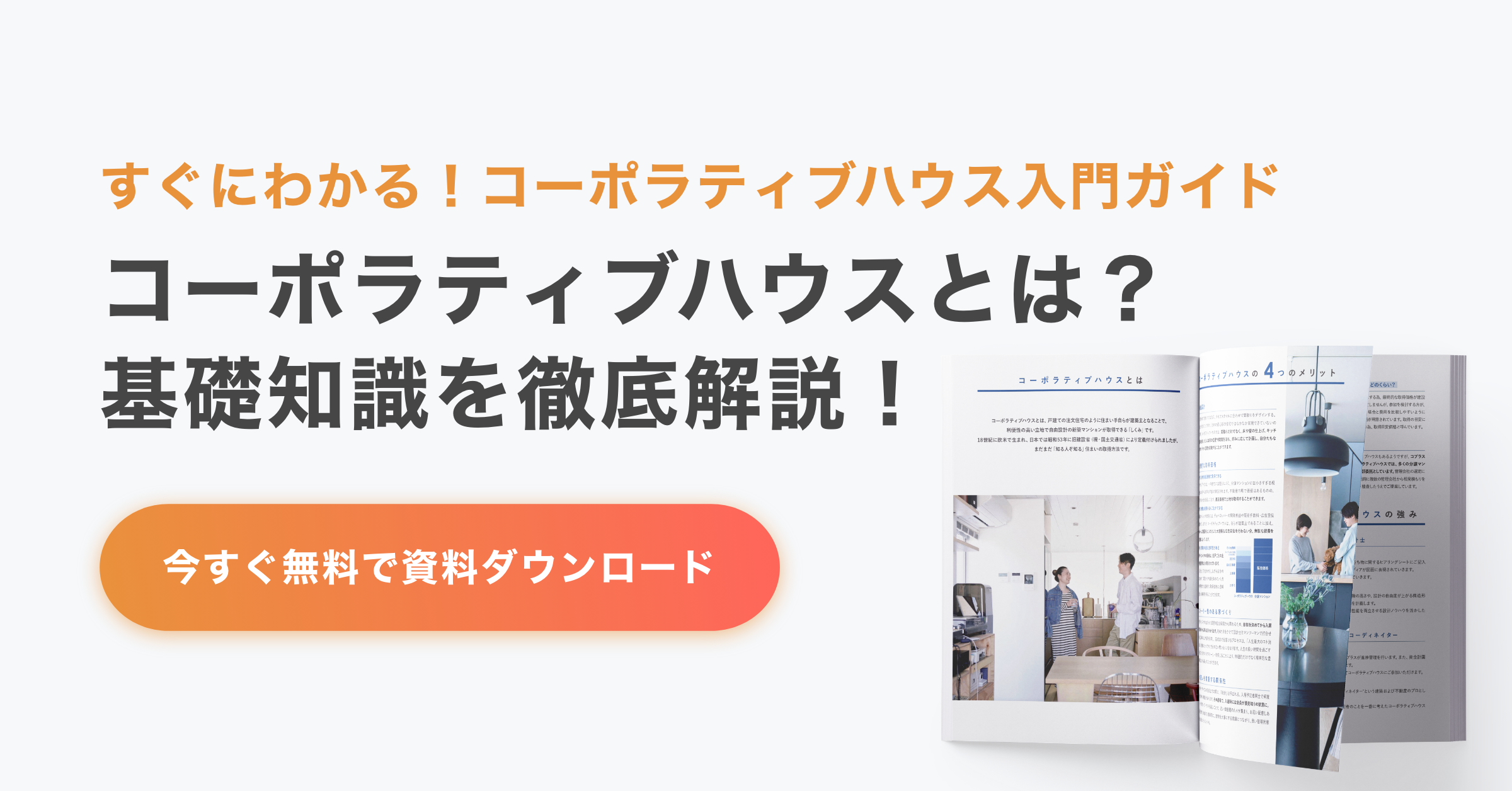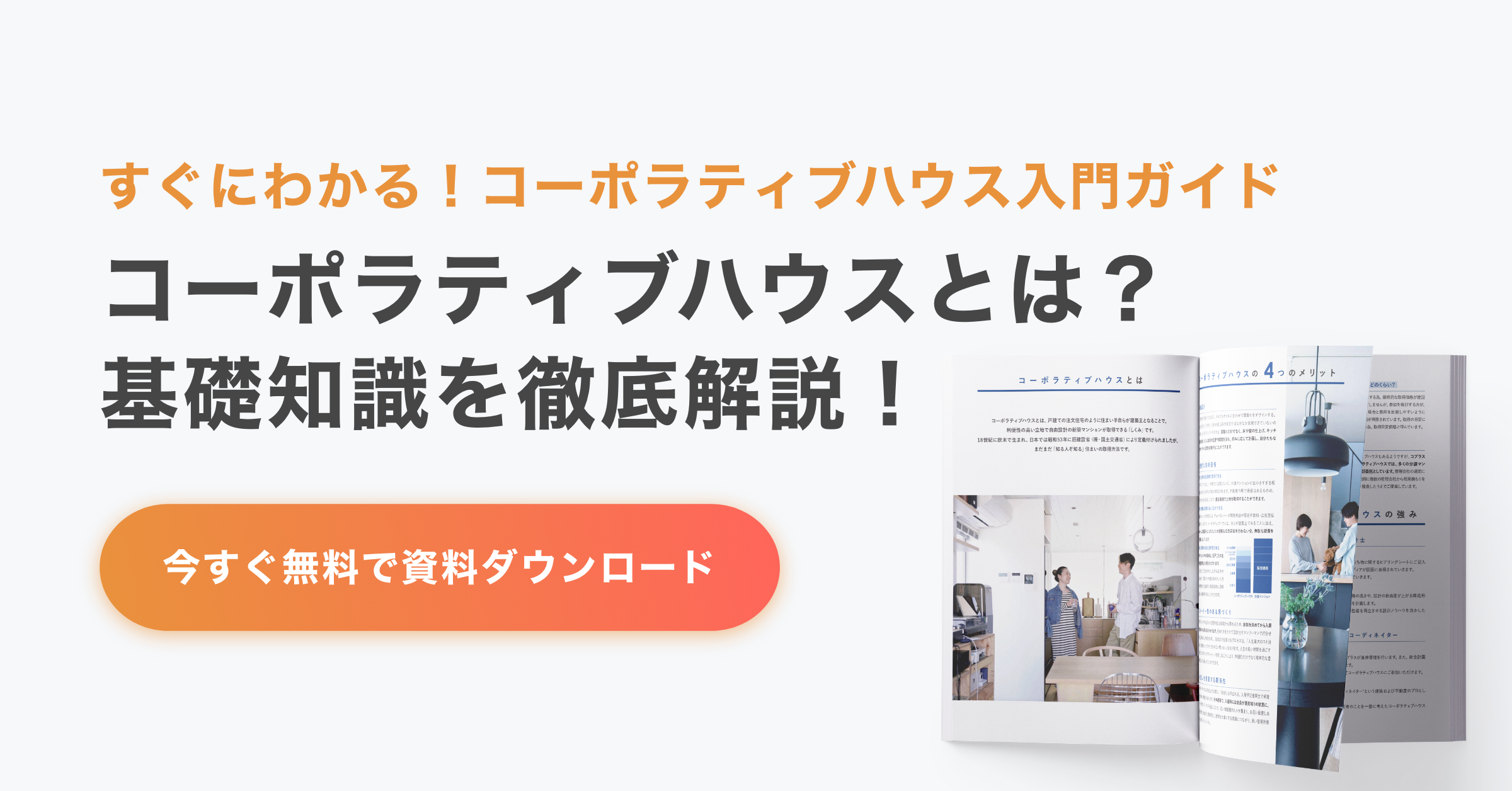年収800万円の人の適正な住宅ローン額とは?返済計画のポイントも解説。
世帯年収800万円となると、日本全体の所得金額の中央値約437万円(2019年厚生労働省公表「国民生活基礎調査の概況」)よりも多く、「どれくらいまで住宅ローンを借りられるか」について気になっている方もいるのではないでしょうか。本記事では、世帯年収800万円でこれから住宅を購入する予定の方に向けて「住宅ローンの借入可能額の目安」や「夫婦で住宅ローンを組む際の注意点」などを解説します。具体的なシミュレーション結果も記載しているので、返済計画を考えるときの参考にしてください。
もくじ
住宅ローンを検討する時の基本的な考え方
住宅ローンを検討する際には、年収額に合わせて適切な予算設定と資金計画が不可欠です。まず初めに基本的な考え方を紹介します。
借入可能額と月々の返済額を考える
一般的には住宅ローンの借入可能額の目安は年収の約5~6倍と言われており、この考え方を用いることでおおよその自分の借入可能額が分かります。
また、会社員であれば、年収から税金を控除した手取り額、個人事業主やフリーランスの場合は、必要経費を差し引いた残額から生活費を差し引いた金額を正確に把握することが重要です。月々の収支バランスを見極め、返済に充てられる金額を算出しましょう。
将来のライフプランやリスクを踏まえて長期的な返済計画を立てる
住宅ローンは最長35年にわたる契約のため、将来のライフプランに合わせた返済計画が必要です。子供の教育費や老後の生活費などを考慮し、将来の見通しを含めた計画を立てましょう。
将来の見通しが立てづらい、という場合は、ライフプランに可変性があることを念頭において、生活を圧迫しない程度の返済額に設定しておくことが大事です。
金利と返済プランを比較し、最終的な返済額を確認する
自分の借入可能額が判明したら、金利のタイプと返済プランを検討しましょう。住宅ローンは借入金額が同じでも、返済期間や金利タイプによって総返済額や月々の返済額が異なります。
複数の金融機関やローン商品の金利を比較し、それぞれのメリットやリスクを理解して自身に合った選択をしましょう。いくつかの質問に答えるだけで自分にぴったりの住宅ローンを提案してくれるサイトを利用したり、ファイナンシャルプランナーへの相談をしたり、するのもおすすめです。
年収800万円の人は住宅ローンはいくらまで組める?

住宅ローンの返済額を考える上で重要な指標が「年収倍率」や「返済負担率(返済比率)」です。住宅ローンを実際に借り入れする前にそれらの指標を理解しておくことで、計画的な返済ができるようになるでしょう。まずは、年収倍率から借入可能額をシミュレーションします。
借入可能額は4000万~4800万円
「年収倍率」とは「購入予定のマイホーム価格が年収の何倍に相当するか」を算出する指標です。
一般的には住宅ローンの借入可能額の目安は年収の約5~6倍。つまり年収800万円世帯の場合、借入可能額は4000万~4800万円が1つの目安になるでしょう。ただし購入する住宅の種類によって、平均的な年収倍率が異なる点には注意が必要。
三大都市圏の中古住宅を購入した人の平均年収倍率は3.81倍(平均購入価格は2894万円)です。それに対して、購入価格が高くなりやすい新築注文住宅の平均年収倍率は6.67倍(平均購入価格は5359万円)となっています。(国土交通省「令和3年度 住宅市場動向調査 ~調査結果の概要(抜粋))
例えば、年収800万円で新築注文住宅を検討する場合、平均年収倍率6.67倍から換算した借入可能額約5300万円と用意できる頭金を合わせた金額が物件価格の上限となります。
ただし、上限額いっぱいで借入するほど、月々の返済額が大きくなることは理解しておきましょう。
無理のない返済額は月々10万~14万円以下
住宅ローンを組む際に、借りられる金額の上限を把握しておくことは重要ですが、それと同じくらい「無理のない返済金額はどれくらいか」を把握しておくことも大切です。
そこで、重要な指標が「世帯年収に占める住宅ローンを含めた年間支払額の割合」を表す「返済負担率」。一般的に無理のない範囲での返済負担率は、手取り年収の20~25%と言われており、30%を超えると返済負担が重くなります。
なお、金融機関の審査基準での返済負担率は35%ですが、これはあくまで金融機関が借入可能額を算出する際の指標であることには注意が必要です。金融機関は個人の返済負担まで考えてくれるわけではないため、自分でコントロールしましょう。
返済負担率の計算方法は、「年間のローン返済額合計 ÷ 手取り年収 × 100」です。
【例】年収800万円(都内在住、40歳未満、扶養なし)の場合
・手取り収入は年額で約635万円(月額で約53万円)
【ケース①】返済負担率が20%の場合
月々返済額:10万6000円 総返済額:4,199万円 ※変動金利0.375%・返済期間35年・ボーなし返済無
【ケース②】返済負担率25%の場合 月々13万2500円
月々返済額:月々13万2500円 総返済額:5,879万円
返済負担率はあくまでも、年収に占める返済金額の割合を示す指標のため、住宅ローン以外にもカードローンや教育ローンなどがある場合は、それらの返済額も含めて返済負担率を計算しましょう。
年収800万円の人が用意する頭金の平均額は?
頭金とは、物件価格に充当できる現金や登記費用、住宅ローンの事務取扱手数料など、現金で用意する諸費用のことを指します。では、実際に頭金はどれくらい用意すればよいのか、次の項目で開設します。
一般的には住宅価格の1~2割、実際には3割程度用意か
できるだけ年収倍率や返済負担率を抑えるには、借入金額を少なくする必要があり、そのためには頭金を用意することがポイントです。住宅購入で用意する頭金は一般的に住宅価格の1~2割程度だといわれています。
ただし、実際には、もう少し高い割合で頭金を用意している人も多い点は留意しておきましょう。
注文住宅の場合、建築費(全国平均で3459万円、三大都市圏平均で3843万円)に対して、自己資金の平均額はそれぞれ972万円(28.1%)と1332万円(34.7%)でした。
多くの世帯で住宅購入資金の3割程度の頭金を用意していることが分かります。(参考:国土交通省「令和3年度 住宅市場動向調査」)
頭金を多く用意することで、借入金額が抑えられたり、支払う利息を減らすことができ、結果的に総支払額が減少する点は大きなメリットです。
ただし、手元にある預貯金のすべてを頭金として入れてしまうと、突然の病気や事故など、不測の事態が起きたときに対応できない恐れもあります。
最低でも毎月の生活費の3カ月分は現金で確保しておくほか、それ以外の出費にも備えるのであれば6カ月分は手元に置いておきたいところです。子どもがいる場合の教育資金など、直近で予定されているライフイベントを考慮しながら、何かあってもしばらくは困らない程度の資金を手元に残すことに留意して頭金の額を検討しましょう。
借入額の検討後は返済期間と金利タイプを考える

ここまで、年収800万円の方が組める住宅ローンの上限額の目安や無理のない返済額などについて解説してきました。しかし住宅ローンは借入金額が同じでも、返済期間や金利タイプによって総返済額や月々の返済額が異なります。
そこでここからは、住宅ローンの利用を前向きに考えている方に向けて、返済期間と金利タイプ別の月々の返済額と総支払額のシミュレーションを紹介します。
【返済期間別】総返済額、月々の返済額はどのくらい?
まずは、返済期間別のシミュレーションを紹介します。
【例】借入金額5,500万円・元利均等返済・変動金利0.375%・ボーナス返済無し
| 借入期間 | 月々の返済額 | 総支払額 |
|---|---|---|
| 25年 | 19万2089円 | 5764万円(総利息264万円) |
| 30年 | 16万1556円 | 5817万円(総利息317万円) |
| 35年 | 13万9754円 | 5871万円(総利息371万円) |
上表のとおり、借入期間を長く設定すればするほど、支払利息が増え、総支払額が増えます。
借入期間25年と35年の総支払額の差は、およそ100万円、年収800万円(手取り年収約635万円)の世帯で借入期間25年の返済を行うと、手取り収入における返済負担率は36%以上になるため、毎月の家計はかなり苦しくなることが予想されます。そのため無理をして借入期間を短くするよりは、最長の借入期間35年で借入を行い、繰り上げ返済を行う方が賢明でしょう。
【金利タイプ別】総返済額、月々の返済額はどのくらい?
次に金利タイプ別の月々の返済額と総返済額をシミュレーションしていきます。
選択する金利タイプによってどれくらいの差が生じるのでしょうか。なお、金利については借入期間中ずっと同率と仮定しています。
【例】借入金額5500万円・返済期間35年・ボーナス返済
| 金利タイプ | 月々の返済額 | 総支払額 |
|---|---|---|
| 全期間固定 (0.940%) | 15万3723円 | 6460万円(総利息960万円) |
| 10年固定 (0.495%) | 14万2650円 | 5993万円(総利息493万円) |
| 変動 (0.375%) | 13万9754円 | 5871万円(総利息371万円) |
選ぶ金利のタイプによって、総利息に大きな差が生じることが分かります。
全期間固定型と変動型の総利息の差はおよそ600万円と、実に2.5倍以上、ただし、変動型には金利上昇リスクがありますが、全期間固定型は返済期間中ずっと同じ金利が適用されるため、そのようなリスクはありません。全期間固定型は低金利の恩恵を受けられないものの、金利上昇局面においても毎月の負担が増えず、計画的な返済ができる点は大きなメリットになります。
なお、年収800万円(手取り年収約635万円)の世帯で、全期間固定型を選択した場合、手取り年収における返済負担率は29%。
そのため、金利上昇リスクが心配で全期間固定型を選択する方は、利用する金融機関を吟味して少しでも適用金利の低いところと契約するとよいでしょう。
全期間固定型のフラット35のなかには、頭金を1割以上入れると優遇金利の適用を受けられるプランがあるのはご存知でしょうか。
仮に0.640%(▲0.3%)で計算し直すと総支払額は6,143万円となり、支払利息が317万円も抑えられます。全期間固定型を選ぶ場合は、そのような優遇金利が適用されるプランを利用して、少しでも総支払額を下げるようにしましょう。
また、頭金を用意することが難しい方や、固定金利と変動金利のどちらにするか判断がつかない方は、10年間だけの固定金利や、固定型と変動型をミックスしたりするという方法も。
住宅ローンを検討する際に金融機関にシミュレーションを依頼して、比較検討してみましょう。
年収800万円の人が夫婦でローンを組む際に気を付けたいこと
昨今の住宅価格の上昇、共働き世帯の増加に伴い、年収800万円の人だけでなく、夫婦でローンを組む場合もあるかと思います。その場合の注意点を以下に解説します。

夫婦で住宅ローンを組む際の住宅ローンの種類
夫婦どちらかだけで希望の借入額に届かない場合、夫婦2人で住宅ローンを組み方法もあります。
夫婦2人で利用できる住宅ローンには、「ペアローン」と収入合算の「連帯債務型」および「連帯保証型」の3種類があります。
ペアローンとは1つの住宅に対して、夫婦それぞれが別々の住宅ローンの契約者となるローン。
1人で契約するよりもトータルでの借入可能額を増やせる点や2人分の住宅ローン控除を受けられる点がメリットの一方で、住宅ローンの契約が2つになることで、契約にかかる諸費用も2本分かかってしまう点はデメリットです。
連帯債務型は夫婦のどちらかが主債務者、もう一方がその連帯債務者となる住宅ローンの契約形態で、民間の金融機関では取り扱いが少なく、フラット35で一般的な方法です。
主債務者でない方も連帯債務者となるため、1つの住宅ローンに対して最初から夫婦それぞれが債務の全額を負う形になります。
ペアローンと同じように、どちらかが単独でローンを組むよりも借入可能額を増やせる点や夫婦それぞれで住宅ローン控除を受けられるのに加え、1本契約自体は1つなのでかかる諸費用も1本分だけで済む点がメリットです。
ただし、返済途中で離婚した場合でも住宅ローンの連帯債務者の返済義務はなくならない点には注意しましょう。
連帯保証型は、夫婦のどちらかが債務者となり、もう一方がその連帯保証人となるローン。連帯債務型と異なるのは、連帯保証人は債務者が返済できなくなった場合に限り、その時点で返済能力があるかないかを問わず、返済義務が生じる点です。ほかのローンと同じく単独で住宅ローンを組むよりも借入可能額は増やせますが、債務者が1人であることから住宅ローン控除は1人分しか適用されません。
夫婦でローンを借り入れる際に気をつけたいこと
夫婦共働きで世帯年収800万円の方が住宅ローンを組む場合に気を付けたいのが、妊娠や出産、親の介護、病気やケガなどライフイベントによって配偶者の収入が減少すること。安定した生活を営むためには、これらの出来事が起こってもマイホームを手放さなくて済むような返済計画を立てなくてはいけません。また老後のことを考えると、定年退職後にも住宅ローンの支払いが残るような返済計画はできれば避けたほうがよいでしょう。
そうしたリスクを抑えるためのひとつの手段として、住宅ローン控除などの減税制度を上手に活用する方法があります。たとえば、住宅ローン控除は年末時点での住宅ローン残高の1割を10年間にわたって所得税や住民税などから控除してくれますが、年間で最大40万円までしか控除されません。つまり、今回のシミュレーションのように総額4000万円以上の住宅ローンを組む場合は、シングルローンを組むよりもペアローンや収入合算の連帯債務型のように夫婦それぞれで住宅ローン控除を受けたほうがお得になることがあります。
コーポラティブハウスという選択肢もおすすめ

コーポラティブハウスとは入居予定者が複数集まって、建設組合を結成し、共同でマンションを建てるしくみのこと。実はコーポラティブハウスには年収1000万円世帯が多く参加しています。
コーポラティブハウスは新築マンションの部類に入るため、住宅ローンも利用可能ですよ。
コーポラティブハウスとは
不動産ディベロッパーがつくったものを「買う」一般的な分譲マンションとは異なり、コーポラティブハウスの場合は、入居予定者がマンションを「つくる」のが特徴です。
コーポラティブハウスのメリット
コーポラティブハウスのメリットは、「利便性の高い立地で、自分のライフスタイルに合わせた住まいを取得できる」ということ。
23区内の人気のエリアを中心に、コーポラティブハウスを企画する会社が土地を取得し、参加者を募ります。参加を決めたら、担当の設計士と打ち合わせを重ね、部屋の間取りや設備を自由に選択することができますよ。
中古マンションのリノベーションとは異なり、窓などの開口部も自分で選べるのが最大のポイントです。
コーポラティブハウスを選ぶときのポイント
コーポラティブハウスに参加する時点では、最終的な部屋の価格が決まっていないため、資金シミュレーションにて余裕を持った住宅ローンの返済比率に設定しておくことが重要です。
とはいっても価格が決まっていないのは不安に思う方もいるでしょう。
コーポラティブハウスを企画する(株)コプラスでは、キッチンや浴室、床暖房などの必要な設備を備えた「取得目安価格」を用意し、検討しやすいしくみにしています。
参加を決めた後に担当設計士との打ち合わせを進めていくことにより、追加費用が決定し、最終的な物件価格が決まります。
ただし、自分の予算を確認しながら、何を採用し何をやめるか選択できるため、納得感の高い住まいにすることができますよ。
まとめ
年収800万円世帯の人の住宅ローンの考え方について解説しました。コーポラティブハウスにも、もちろん住宅ローンは利用可能なため、住まい探しの選択肢のひとつとして検討してみるのはいかがでしょうか。
(株)コプラスでは住宅ローンのシミュレーションもサポートしているので、お気軽にお問い合わせください。

執筆者:株式会社コプラス
渋谷区にあるまちづくりが得意な不動産コンサルティング会社。コーポラティブハウスの企画をメイン業務としながら、家づくりに関する知識をお届けするデジタルコラム・「CO+コラム」も運営しています。
◆コーポラティブハウス特設サイト https://cooperativehouse.jp/
◆お宅訪問インタビュー動画: https://cooperativehouse.jp/casestudy/
◆コプラスの仲介サイト: https://cooperativehouse.jp/agency/
この記事を書いた人
株式会社コプラス